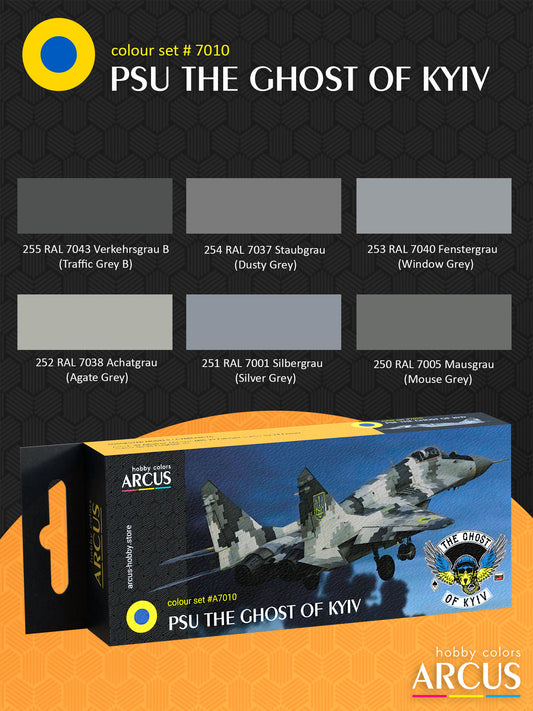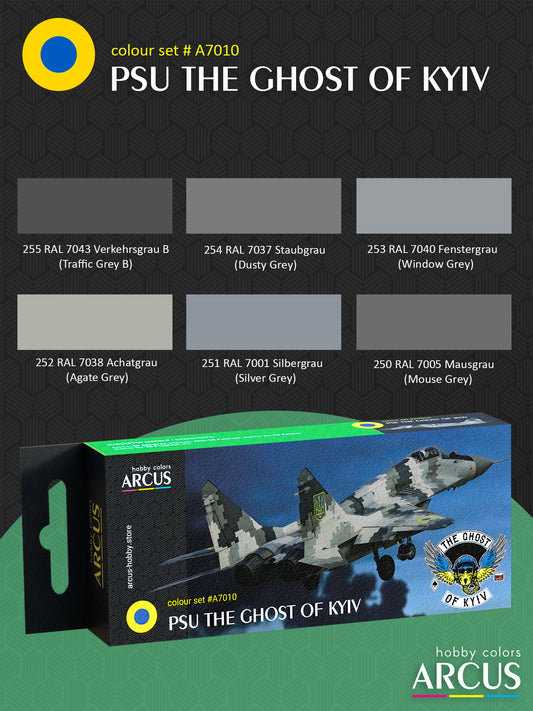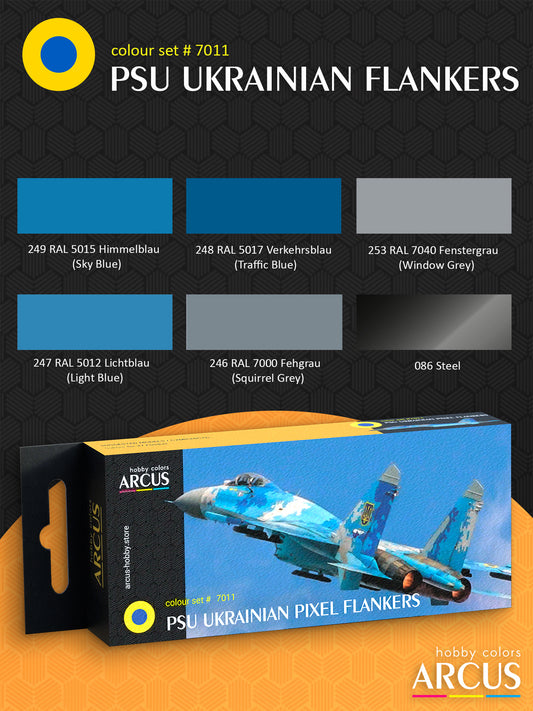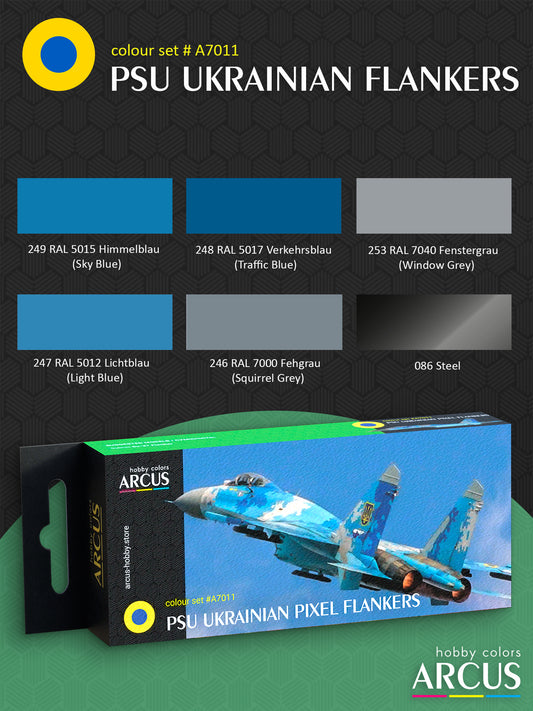戦間期におけるドイツ陸軍
第一次世界大戦の終結後、ドイツ軍は1919年1月に正式に解体された。しかし、同年3月には新たな暫定的な軍隊としてライヒスヴェーア(Reichswehr)を編成することが政府によって決定され、将来の防衛力の基盤とされた。数か月の移行期間を経て、1921年1月に正式に設立が認められた。1919年のヴェルサイユ条約の条件により、ドイツ軍の規模や武装は厳しく制限され、部隊は国内治安維持と国境警備のみに使用が許可されていた。口径105mmを超える砲兵装備、装甲車、潜水艦、大型軍艦などの重装備はすべて禁止され、空軍の創設も認められていなかった。
武力衝突におけるライヒスヴェーアの役割
1920年代初頭の混乱期において、ライヒスヴェーアは主に左派勢力による反乱の鎮圧に使われた。とりわけ1919年1月のベルリン蜂起では、スパルタクス団(Spartakusbund)による武装蜂起に対処した。同時に、防衛任務の多くは、ヴェルサイユ条約の制約を受けなかった義勇軍フライコール(Freikorps)によって担われた。ライヒスヴェーアに十分な戦力がなかった地域、たとえばポーランドやリトアニアの義勇部隊との国境衝突や、1920年にルール地方の産業地帯で発生した左派反乱における労働者民兵「ルール赤軍(Rote Ruhrarmee)」との戦闘などが該当する。1923年10月から11月にかけてのザクセン州およびテューリンゲン州への「帝国執行(Reichsexekution)」では、中央政府の命令により、ライヒスヴェーアは右派民族主義的な義勇兵部隊と連携して、これらの地域の左派政府を打倒した。ライヒスヴェーアの将軍たちは、「シュタールヘルム(Stahlhelm)」や「キッフホイザー同盟(Kyffhäuserbund)」など、ワイマール共和国に反対する右翼退役軍人団体と密接な関係を持っていた。
1921年以降、ライヒスヴェーアはヴェルサイユ条約に反し、秘密裏に新兵器の開発と空軍力の再建に着手した。その際、ソビエト赤軍との協力体制が築かれた。ドイツは最新技術の研究に投資し、兵士の訓練をソビエト連邦領内で行うことができた。
このドイツとソ連の軍事協力は、両国にとって利益があった。ドイツはソ連の軍需産業の発展を支援し、ソ連の将校たちはドイツの軍事アカデミーで高度な訓練を受けた。一方で、ライヒスヴェーアは西側諸国の監視を逃れて、新型兵器の試験や部隊訓練をソ連領内で行った。ソ連のリペツクには共同の航空学校が設立され、ドイツの教官たちが約120人のソ連パイロット、100人以上の航空偵察員、および約30人の整備士を指導した。一部の訓練はドイツ国内でも実施された。この協力の主な目的は、ヴェルサイユ条約の禁止にもかかわらず、将来のドイツ空軍のための人材と戦術の基礎を構築することであった。
1923年、フランスとベルギーによるルール地方の占領は、ワイマール共和国にとって大きな試練となった。ライヒスヴェーアは、条約上の制限と国内の不安定な政治状況により、対応することができなかった。同年11月、バイエルンでの極右クーデター「ビアホール・プッチ(Beerhallputsch)」のさなか、フリードリヒ・エーベルト大統領は国防大臣オットー・ゲスラーに非常権限を委譲した。この決定により、ライヒスヴェーアは純粋な防衛力から体制維持の政治的手段へと役割を転換した。
1925年のロカルノ条約とドイツの国際連盟加盟により、ラインラントは非武装地帯とされた。1930年までに、議会制民主主義の崩壊と大統領令による統治の拡大により、ライヒスヴェーアの影響力はさらに増した。フランツ・フォン・パーペンと将軍クルト・フォン・シュライヒャーは、ライヒスヴェーアを用いてワイマール共和国を打倒することさえ検討していた。
1935年、ライヒスヴェーアは正式に解散され、アドルフ・ヒトラー政権はヴェルサイユ条約に反して大規模な再軍備計画を開始した。3月1日にはルフトヴァッフェが設立され、同月16日には徴兵制が導入された。同日に旧ライヒスヴェーアは新たにヴェアマハトという名称に改称された。
ドイツ軍迷彩塗装の変遷
第一次世界大戦終結後、従来の単色フィールドグレイ「Feldgrau」による塗装は、現代戦に適さないことが明らかになりました。1918年には、軍用車両への三色迷彩の導入を求める初の命令が出され、1920年5月12日には陸軍総司令部(Heeresleitung)が新たな多色迷彩「Buntfarbenanstrich」を正式に導入しました。この塗装には、緑、黄、茶の斑点が用いられました。初期は手作業で塗られていましたが、後にはスプレー塗装が導入され、より迅速かつ均一に塗装されるようになりました。
1922年、公式公報 H.V.Bl. 1922年第24号により、この迷彩は戦闘用車両—装甲車や砲兵トラクターなど—のみに適用されるとされました。その他の車両は引き続き標準のFeldgrauで塗装されていました。Buntfarbenanstrichはヴェアマハト創設初期にも使用されており、車両の製造時期やメーカー、車種によりパターンには若干の違いがありました。それでもこの三色迷彩は広く認識され、戦間期のドイツ軍における迷彩発展の重要な一段階となりました。
ドイツ軍の色彩規格
1925年4月23日、ドイツ政府は供給条件国家委員会(Reichsausschuss für Lieferbedingungen、略称RAL)を設立しました。形式上は経済省の下にありましたが、法的には独立した組織として運営され、製品規格の標準化、とりわけ産業、交通、軍用分野における統一的な色彩体系の導入を目指していました。
最初の統一色規格であるRAL 840は1927年に発表されました。この体系により、塗料の大量生産が可能になり、重複を避けてコスト削減を実現しました。当時のドイツは外貨不足に悩まされており、輸入顔料に頼ることが困難だったため、主に国内産の顔料が使用されていました。以降、郵便、鉄道、その他の公共機関の要請に応じて、色数は徐々に拡張されていきました。
同年には輸送部門向けにRAL 840 Bという別規格が導入され、40種類の車両用カラーが定義されました。1932年にはこの規格が更新され、誤解を避けるためにRAL 840 B2と改称されました。その後も色の追加が進み、「Ergänzungsblätter(追加色票)」として発行されていきました。